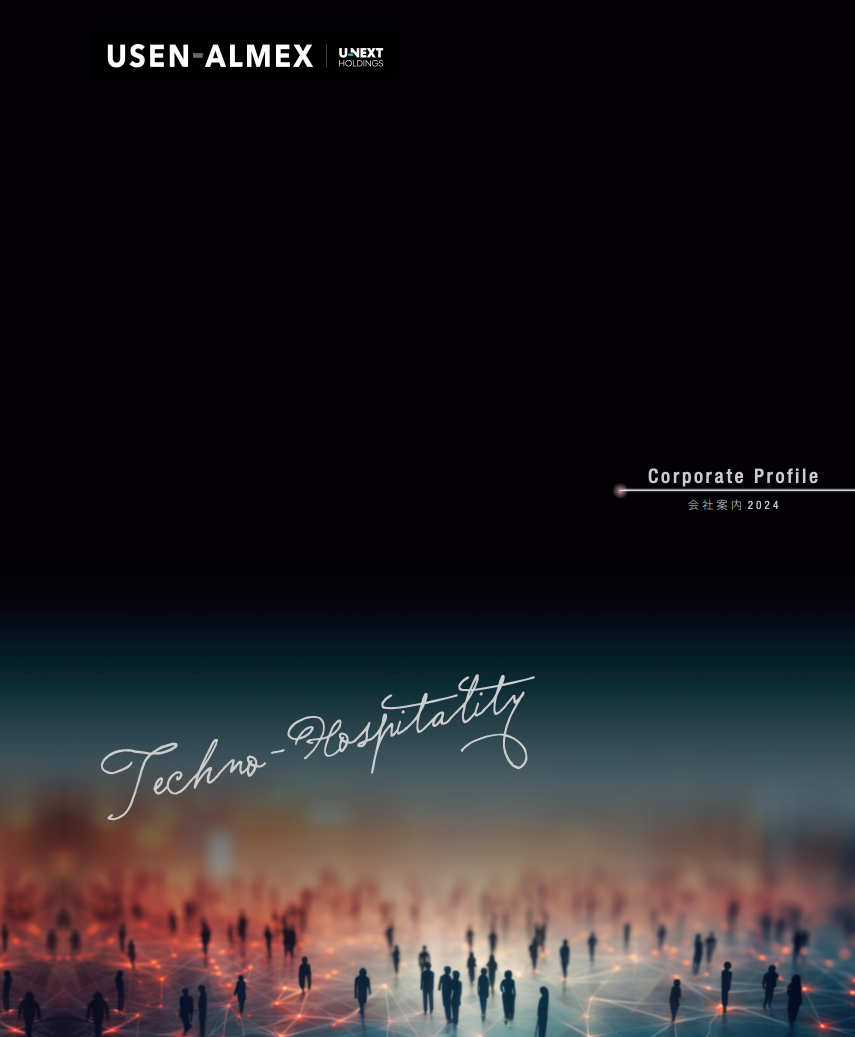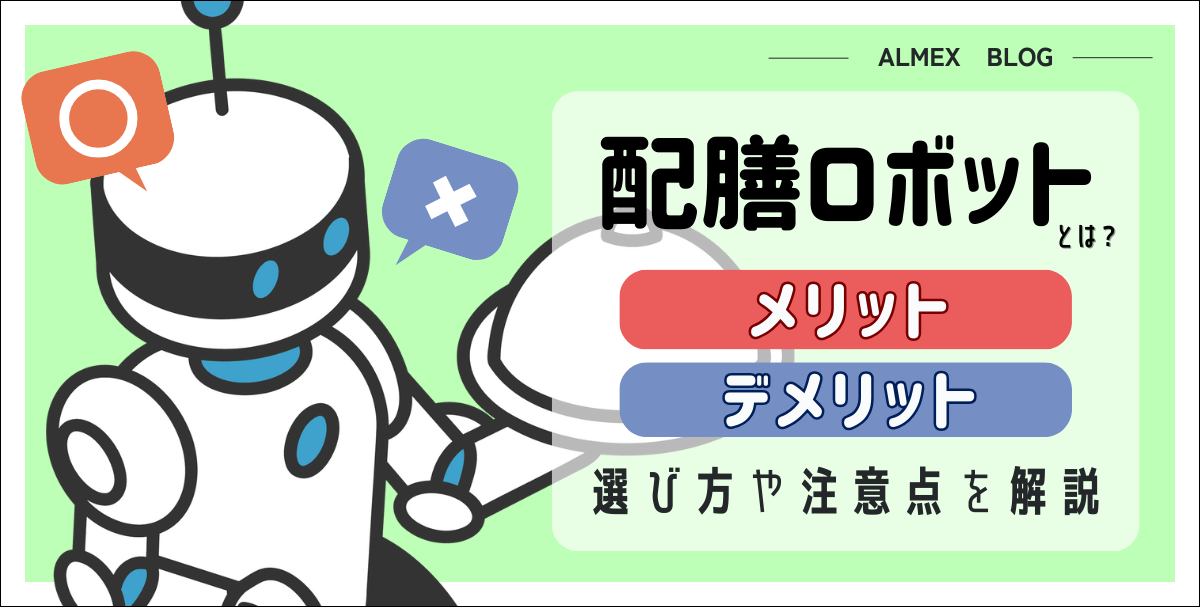配膳ロボットとは
配膳ロボットとはどのようなものか、「概要」と「仕組み」について解説します。
配膳ロボットの概要
配膳ロボットとは、料理や飲み物を客席まで運ぶことに加え、空いた食器を回収して下げる役割を担うロボットです。飲食店に限らず、医療施設やインターネットカフェなどで導入が進んでおり、特に人手不足が課題となっている業界で注目されています。
配膳ロボットの仕組み
配膳ロボットは、行き先を指定しスタートボタンを押すことで、運搬を開始します。歩行者のほか、椅子やカバンなどの小さな障害物を避けて目的地に到着可能です。配膳ロボットには自立走行機能が備わっており、「マーカー(タグ)」「マッピング」いずれかの設定で、自由に施設内を走行できます。
配膳ロボットの主な役割
配膳ロボットの主な役割は、「料理や食器を運ぶこと」と「適したルートを自走すること」の2点に分けられます。
それぞれについて解説します。
食器や料理、ドリンクを運ぶ
客席に料理や飲み物、空いた食器を運ぶといった作業は、配膳ロボットの最も基本的な機能です。配膳ロボットには、複数のトレイが設置されているため、人が行うよりも効率的に作業を実施できます。
障害物を避けながら最適なルートを自走する
配膳ロボットは、あらかじめ設定した目的地まで自走が可能なため、人がつきっきりで作業する必要がありません。内蔵カメラやセンサー機能が搭載されているため、人や障害物を検知して安全に回避しながら走行します。走行スピードも穏やかなため、お客さまや店舗スタッフも安心して配膳ロボットを避けられます。
配膳ロボットが普及した背景
配膳ロボットが普及した背景には、「人手不足」と「人件費の高騰」があります。それぞれを詳しく解説します。
慢性的な人手不足のため
配膳ロボットが普及した背景として、少子高齢化の影響により労働人口が減少したことが挙げられます。サービス業を中心に、慢性的な人手不足が深刻な課題となっています。こうした背景から、業務の一部をロボットに任せることで、人手不足の解消、従業員の身体的な負担軽減のために配膳ロボットの導入が進められています。
人件費が高騰しているため
人件費は企業の大きな負担です。東京都の場合、最低賃金は2014年から2024年までの10年間で888円から1,163円と、275円ほど上昇しました。このような人件費の高騰は全国的な傾向で、2023年度から2024年度の1年間で、全国で4〜6%最低賃金が上昇しています。配膳ロボットは人に代わって業務を担うことができるため、長期的な人件費の抑制にもつながります。
※参考:厚生労働省
※参考:地域別最低賃金の全国一覧 |厚生労働省
配膳ロボットを導入するメリット
配膳ロボットの導入は、飲食店や医療施設が抱える課題の解決につながります。ここでは、3つのメリットについて解説します。
業務効率化につながる
配膳ロボットは、一度に多くの料理や飲み物、食器の運搬が可能です。これにより、従業員の厨房と客席の往復を減らせるため、業務効率化に貢献します。また、従業員は、配膳や片付けといった作業にかかっていた時間をお客さまとの会話やおもてなし、電話対応などに費やせます。案内スピードが上昇し、生産性の向上にもつながります。
集客効果が期待できる
配膳ロボットを導入している飲食店や医療施設は増加傾向ですが、まだ導入店舗は限られています。配膳ロボットがあることをPRすれば、集客効果が期待できるでしょう。配膳ロボットが施設内を従業員やお客さま、障害物を避けながら動き回る姿は斬新で、話題性に富みます。SNSやテレビなどで取り上げられれば、配膳ロボット見たさに来店する層の獲得にもつながるでしょう。
人手不足が解消される
料理の配膳や空いた食器の片付けなどを配膳ロボットに任せることで、少ない人員でもサービスを提供できるメリットがあります。新型コロナウイルス感染症の影響で飲食店の従業員は減少しました。2022年以降、飲食店への求職者は増加傾向にあるとはいえ、微増にとどまっており、売り手市場であることに変わりはありません。
従業員の負担が大きい業務を配膳ロボットが対応することで、働きやすい環境が整い、離職率が低下します。そのため、無駄な求人コストも減らせるでしょう。
配膳ロボットを導入するデメリットと課題
配膳ロボットは、業務効率化や利益向上などメリットがある一方で、デメリットもあります。
ここでは、3つのデメリットについて解説します。
導入コストがかかる
配膳ロボットを導入する場合、相応の費用がかかります。配膳ロボットは、「買取式」と「レンタルリース式」がありますが、買取式の場合、1台あたり100〜300万円ほどの費用が必要です。レンタルリース式の場合、1か月で8〜10万円ほどの費用がかかります。毎月の負担額は抑えられますが、総額で考えると買取式よりも高額になるでしょう。
導入に際して、ロボットが通行しやすいように通路幅の調整や、段差をスロープに変えるといった改装が必要な場合、さらにコストがかさむでしょう。また、ロボットの運用には、インターネットへの接続が必須なため、施設内のネット環境の整備も必要になります。
従業員への周知が必要である
配膳ロボットを導入する際は、操作説明を含め、運用方法について従業員に周知しなければなりません。必要に応じて、店舗スタッフのオペレーションも変更が必要でしょう。状況によっては、オペレーションの変更が従業員の負担になる場合もあります。
たとえば、「どのような状況で配膳ロボットを活用するのか」、「店舗スタッフはどのように動くのか」など、あらゆる状況を想定し、運用ルールを明確にしておくことで、現場の混乱を避けることができます。
コミュニケーション不足になる可能性がある
配膳ロボットを導入することで、配膳時や空いた食器の回収時に行っていた、お客さまとの直接的な会話の機会が失われます。お客さまと触れ合い、コミュニケーションをとる機会が減れば、距離感が生まれやすくなるでしょう。広まった距離を埋めるためには、接客サービスを改善したり、積極的なコミュニケーションをとったりして顧客満足度を向上する工夫が必要になります。
配膳ロボットの選び方
配膳ロボットの選び方を「機能」、「サポート体制」の2つの視点から検討することが重要です。
それぞれのポイントを詳しく見ていきましょう。
機能から選ぶ
各メーカーから、用途に合わせたさまざまな機能を持つ配膳ロボットがリリースされています。たとえば、接客効果を高めたいのか、配膳や運搬効率を重視したいなど、求める機能は多岐にわたります。予算と比較して、自社に必要な機能から配膳ロボットを選びましょう。また、POSレジ・オーダーエントリーシステムなど、ほかのシステムと連携できることも、配膳ロボットを選ぶ基準になります。
サポート体制から選ぶ
配膳ロボットを導入したら、従業員が操作方法を覚えなければなりません。運用が始まってから故障したり、メンテナンスが必要になったりすることもあるでしょう。導入後のサポート体制や保守サービスの充実度も選択する際のポイントになります。
操作方法がわからず、うまく運用できなければ、かえって店舗スタッフの負担になりかねません。万が一のトラブルや故障、事故などに対応できる体制が整っているかも重視し、事前に確認しておくと安心です。
配膳ロボットを導入する際の注意点
導入の目的を明確にする
配膳ロボットを導入する際は、目的を明確にすることが重要です。たとえば、人件費を削減して少人数営業を強化したい、業務負担を軽減して接客力を底上げしたいなどが考えられます。目的を共有し、自社に合った機種を選ぶことが大切です。
予算を明確にする
配膳ロボットを複数台導入しようとすると、それだけコストがかさみます。予算の都合上、配膳ロボットを複数台導入することが難しい場合もあるでしょう。予算が限られている場合は、リースやレンタルを利用したり補助金を活用したりしましょう。導入する前に予算を明確にし、費用面で余裕があるか、慎重な検討が必要になります。
オペレーションを明確にする
配膳ロボットのメリットを生かすために、配膳ロボットありきのオペレーションの構築が求められます。配膳ロボットが活動しているとき、店舗スタッフはどのように動くべきか、全体の流れをていねいに組み立てましょう。事前にオペレーションを細かく設定しておくことで、スムーズに業務が遂行できます。
配膳ロボットを導入する手順
配膳ロボットは、以下の手順で導入しましょう。
1.複数企業から資料を取り寄せ、配膳ロボットの機能やコストを比較検討する
2.配膳ロボットが決定したら、テーブル配置の変更や音声登録などの導入までの準備を進める
3.運用を始める前にシミュレーションを行い、適宜修正を進める
4.配膳ロボットを組み込んだオペレーションを店舗スタッフに共有する
5.運用中に事前の想定とは異なる課題が生じた場合、現場の意見も取り入れて改善を進める
まとめ
配膳ロボットを導入することで、人手不足の解消や業務効率化、利益向上に役立ちます。導入を検討する際は、機能やサポート体制から自社に合ったものを選びましょう。
USEN-ALMEXでは、ホテルや旅館などの宿泊施設や医療機関を筆頭に、さまざまな業種へ配膳ロボットや自動精算機を提供しています。人手不足を解消し、業務効率化を進めたいときは、導入をご検討ください。
この記事を書いた人
USEN-ALMEX公式SNS